夏休みの終わり、8月31日に口蹄疫関連ドラマ「命のあしあと」が再放送されていました。2010年4月宮崎県で国内では10年ぶりに発生した口蹄疫は、畜産の盛んな地域を蹂躙し、牛や豚合わせて約30万頭の犠牲をもたらし、さらには地域の経済や生活にも多大な被害をおよぼしました。4月の発生以来、8月27日の終息宣言まで約4か月におよぶ事態をドラマにされ、昨年度NHKのBSで放映されたものですが、残念ながら我が家では諸般の事情で見ることができずにおりましたので、新聞の地上波テレビ欄で見つけたときはラッキーと思い、見ることができました。主題は、口蹄疫に巻き込まれた農家の観点で描かれていました。自分たちが得た情報の大半が見てきた第三者によるものであったので、陣内孝則さんほかの生産者役を演じたかたがたの気持ちのゆれにあらためて感じるところがありました。惜しむらくは、一家族のストーリーが主流だったので、地域に多大な影響があったというのが感じにくいのではなかったかと思いました。
とはいえ、陣内氏演じる農家の悩みやその子が発する疑問、殺処分に対して「人間ならどうするの?」など何度も考えるべきことがいっぱいでした。あれから約3年がたちました。よく思うことで、農家のかたがたを前に話すことですが、「もう3年も前のこと」「たった3年前のこと」など思いはいろいろかと思います。でも、海外特に東アジアを見ていると、まん延していると言ってもいい状況です。この3年にどういうことができたかを考えるべきかと思うのですが。(2013年9月)
命のあしあとHP
食料自給率をあげる
盛会に終わった長崎豚まつりですが、その中で世界的な食糧危機に対するメンバーの熱い気持ちを聞く機会がありました。曰く、世界人口は紀元0年には2億人、それが3億人に達するのに1000年かかったのに、次の1000年で急増し、最近の200年では爆発的な増加をしており、2050年には100億人近くなるといわれています。そうなると今後食糧はどうなるのでしょうか。現状で、日本の食料は大半を輸入に頼っています。今のところ、お金を出せば食べ物は手に入りますが、今後の人口増加の中ではいかに。それから、よく聞かれる地球温暖化に影響する炭酸ガス増加と水不足があります。食料輸入に際しては、それをつくるための水を輸入していることになりますし、さらには生産や輸送に伴って炭酸ガスを排出しています。その一方、日本の農地は減少し、担い手も高齢化で危ういことこの上なしです。メンバーが言うように、ほんとにこのままでいいのでしょうか。(2008年12月)
新型インフルエンザはいかに?
近頃テレビでしばしば特集されています新型インフルエンザですが、ひとたび発生すれば、誰も免疫を持たないので日本国内で64万人が死亡すると言われています。例えば、新型インフルエンザが発生したある国で感染したビジネスマンが帰国して、成田空港の検査をすり抜けた場合、数日後には数千数万の感染を引き起こすそうです。警戒するのは十分すぎるほど必要ですが、その一方で、実態を知ることも必要だと思います。
新型インフルエンザは、鳥インフルエンザが変異して発生するとされていますが、先日その鳥インフルエンザのアジアにおけるシンポジウムに参加しました。その中で、北海道大学の喜田先生によれば、現在、東南アジアでみられる人感染の例では、約400人が感染し、うち6割が死亡していますが、それらは鳥インフルエンザ死亡鶏処理などに深く関わった人だそうです。ところで、これまでの世界的流行、つまりスペインかぜや香港かぜなどでは、弱毒の鳥インフルエンザが人型インフルエンザになって人を襲っています。今回は強毒の鳥インフルエンザ、つまり鳥に全身感染し、急死を引き起こす伝染病がそのまま人の新型になることを危惧されるところですが、現在みられている患者は、肺炎が主体で、全身感染にはいたっていない。となると、20世紀初めの頃より抗生物質など医療は進んでいますから、対応の方法もあるかも。それから、現時点では、人から人への感染は認められていないようですし、ウイルスの遺伝子レベルの調査でも鳥の中で変異して新型になることもないと考えられています。そう考えると、今現在の日本では新型インフルエンザという言葉をやみくもに恐れる必要はないと思いますが、最新情報とそれから毎年の季節性インフルエンザで1万人ほどが亡くなっていることも知っておくべきことだとも言われました。(2008年12月)
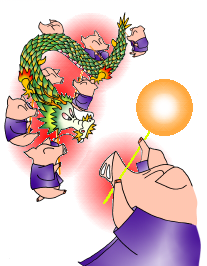 第2回ながさき豚まつりが開催されます
第2回ながさき豚まつりが開催されます2007年に引き続き、今年もながさき豚まつりが開催されます。昨年の手探りの中での実行と違い、今年は皆さん気合が入っています。昨年の経験を活かし、いかに消費者にアピールするかを各担当が知恵を絞っていますが、とりわけ後継者グループの意気込みはすごいものがあります。いろんなイベントを考えていますが、その根底には、よい長崎県産豚肉をなんとかして消費者の方々に知ってもらいたいという気持ちであふれています。(2008年10月)
豚まつりは、天候が心配されましたが、昨年より多くの方々(約800名)に参加いただき盛況に終わりました。
実は、就職するまで、家畜保健衛生所という名前は知っていましたが、業務はよく知りませんでした。家畜の獣医師というと、診療業務が一番イメージしやすいのですが、では他にはどんな仕事があるんだろうなどと考えていました。
最初の仕事は、黒毛和種牛の繁殖検診でした。長崎の和牛どころのひとつ、五島列島で先輩に教えてもらいながら、農家をまわって直腸検査をし、繁殖成績の向上に努めていました。それから、病性鑑定の細菌検査担当として、牛や豚などの下痢や肺炎から分離した菌と培地に埋もれる日々を過ごしましたし、国境の島、対馬であか牛の診療にも従事しました。養鶏の盛んな県南島原半島に勤務し、現在は、県央地区で養豚養鶏を担当し、生産性向上のための検査や衛生対策指導をしていますが、昨今では病気でないのはあたりまえ、さらに畜産物の食品としての安全安心が求められるようになり、動物由来感染症対策にかなりの時間を費やしています。
家畜保健衛生所でこのところ最も注目されているのは、BSE監視や高病原性鳥インフルエンザ防疫などの伝染病対応でしょう。検査や予防対策指導に加えて、万一の発生があった時の防疫準備をしていますが、これは、家畜保健衛生所だけでなく、県や市町など関係機関との連携が必須です。
家畜保健衛生所に勤務して思うのは、業務が多様なこと。衛生関連の他にも、肉用牛の育種や畜産としての環境保全、養豚養鶏の振興、食の安全関連などそれぞれの担当ががんばっています。加えて、長崎県は、北は韓国を望む対馬から、南は温暖な島原半島まで広範な県域を持ち、それぞれの地区に特色のある畜産があり、それぞれの地域の人と協力しながら仕事をしています。
私自身、大阪府の出身ですが、海のそばで仕事する事が希望でしたので、行く先々にきれいな海があり、いろんな人と仕事ができる現状を楽しんでいます。(2008年7月)
家畜保健衛生所職員のメッセージ集へ
アンケートの愛国心
中国産冷凍ギョーザの問題が出る少し前だったのですが、食の安全安心に関わる講演会に参加しました。講師は、西日本新聞で農業と食を追求されている佐藤記者です。
店頭でアンケートをとると、国産品が良いという人は80%になるそうです。なるほどそうかとも思いますが、でも考えてみると、日本の食料自給率は確か40%弱?。だとすると、皆さん何を食べているのでしょう。別のアンケートで、購入についてより細かく分けると、健康志向でよいものを選んでいる人や全く無関心な人、ひたすら安価な物に手を伸ばす人が多くを占め、関心もあり、農業など生産にも気が向くのは5%程度。先の結果と比べて、そのズレはアンケートの愛国心と言われるのだそうです。
今ならもう少し安全志向、おそらく国産指向かもしれません。これを単なるブームでおわらないようなキャンペーンが必要ではないでしょうか。単に中国産だからダメというのではありませんが、何か問題があった時に、手を打てる状況下にあることが最低限の条件ではないでしょうか。食というのは生命活動の大元でしょう。現在、にわかに国産の野菜が高騰し、その品薄がクローズアップされていますが、佐藤記者曰く、店頭の品揃えは、消費者の意向の表れなんだそうです。これまでの傾向が輸入品頼りになっていたと言うことでしょう。今、この機会に考えるべきではないでしょうか。(2008年3月)
この数年、畜産物の価格は比較的堅調であったと言えると思います。しかしながら、畜産農家からあまり元気のいい声は聞こえてきません。生産費が、特に昨年から異常に値上がりしているのです。生産費に大きな割合を占める飼料は、その多くを輸入に頼っていますが、まず石油の値上がりによる輸送費が上がっています。さらに、昨年くらいからよく聞かれるバイオ燃料の影響があります。石油一辺倒からの転換とはいいますが、その原料はトウモロコシなどの穀物ですので、限られたトウモロコシを車と家畜で取り合うことになっているのです。地球温暖化など環境問題は、小学生の冬休みの作文課題にもなっていましたが、調べてみるほどに、危機的な状況であることがわかり、がく然とします。そんな状況下では、賛否はあるとしても、取り組みの流れは変わることがないのかも。
飼料代がこのまま高値で推移するなら、畜産農家の生産コストを減らす努力も限界に迫っています。物の価格は、需要と供給の関係で決まるもので、これこれの経費がかかるからという理由で決めるものではないとは、いつか農産物価格に対して、経済の専門家の一人が意見を言われていましたが、現在のままの畜産物の価格では、生産自体が成り立たなくなるかもしれないのです。実際、泣く泣く廃業された方もいらっしゃいます。食の安全安心とはよく言われますが、もう一つ安定供給というのも加えてみるのはどうなんでしょう。(2008年1月)
畜産物の生産コスト上昇にご理解を! 長崎県畜産課情報
毎年、秋に長崎県種豚共進会を開催していました。共進会というのは、各農場が自慢の豚を持ち寄り、発育や品種の特長を競い合うコンテストです。長年にわたり、それを機に飼養技術の切磋琢磨をしてきました。でも、今やただ技術向上のみならず、その成果をアピールするべきだ、なにか消費者向けのイベントに出来ないかということで、関係者一同、協力して計画したのが、ながさき豚まつり。自慢の豚、そして自慢のおいしい豚肉を準備して去る10月28日、さわやかな秋空の下、開催しました。
どのくらいの人が集まってくれるんだろうと心配しつつ、早朝から会場を開けましたが、時間になると多くの人々の参加をいただきました。豚肉販売や試食コーナーなど、おかげで盛況でしたし、共進会の予想投票にも100名以上も参加していただきました。来場いただいた方々には、県産豚肉のよさをわかっていただければ幸いですし、さらに言えば、現在の養豚、もっといえば国内の畜産がおかれている状況をわかっていただけるような活動が今後も重要でしょう。(2007年11月)
消費者交流会に出席しました
先日、養豚関係者と消費者の方々との交流会に出席する機会がありました。会は、生産者の熱いアピールから始まりました。まずは自己紹介のはずが、うちの農場では、長崎のいい環境の中、こうして良い豚を育てているということを話しているうち、ついつい自分こそが一番と言いかねない熱の入りように、生産者が互いに苦笑する場面もありました。それに対して消費者側も極めて真剣に、生産現場を勉強しにきたことを告げられ、良いムードで会が進みました。
養豚協会長曰く、「これまでは、養豚農家が集まって技術研鑽し、いい豚を作る、でよかった。しかし、昨今は、こんないい豚を作っている、そして安心安全をきちんとアピールしないといけないと考えている。」消費者の方々からは、「国内産の安心安全のポイントは何?」「長崎県産はどこで買えますか?」「飼料を国産で賄えないの?」という率直な質問が出ました。これに対して、飼育に関する記録、どんな餌・どんな薬を使いましたをきちんと残す、流通面までなかなか関われないけれども、ここのお店には出してもらってる、飼料は輸入だけどいいものを吟味しているなど、生産者の面々から丁寧な回答がありました。さらに、最近ではバイオ燃料需給の影響による飼料代の急騰や貿易協定の問題による輸入肉の増加、食糧自給率をどうやってあげるのか、などに話が進みました。かたや安全安心な豚肉を生産していると言い、かたや安全安心な豚肉を求めているのに、なぜかスムーズに行ってない。行政は何をしているんだ、と言う話になり、にわかにとばっちりが回ってきました。でも最後は、養豚協会の面々の得意豚肉料理のふるまいで、和やかに終了となりました。この会を、今後どのようにしていくのかが、実は一番の課題だと思います。(2007年6月)
今年初めに宮崎と岡山で発生した高病原性鳥インフルエンザは、関係者により迅速的確な防疫が講じられ、その後の続発もなく、つい先日5月8日に清浄国に復帰することができました。長崎県もそうですが、どこの県も今回の例に習って対策を練り直していることでしょう。
ところで、鳥インフルエンザ対応がそろそろ終盤に近づいていた去る4月1日、家畜衛生分野ではひとつの大きな成果が公表されました。長年、日本の養豚産業を苦しめていた豚コレラという病気が日本から無くなったという宣言がなされたのです。豚コレラは、強烈な豚の伝染病で、子豚、親豚あらゆる豚に急速伝播し、急死してしまうので、ひとたび発生すれば、広範囲に甚大な被害をもたらします。豚コレラと言う名前は、人のコレラとは全く関係ありませんが、たくさん死ぬと言うことから名を借りて付けられています、念のため。先輩方の話をお聞きすると、かって獣医師の養豚分野の仕事のかなりの部分が豚コレラ防疫に費やされていたようですが、昭和40年代のワクチン普及以来急減し、平成4年を最後に国内での発生は見られなくなりました。平成12年以降は、ワクチンを使わずに、計画的に全農場を検査しつつ監視してきましたが、このほど撲滅宣言と相成りました。安全安心な豚肉生産の基本は健康な豚であることは当然です。もちろん、現在も養豚業はいくつかの疾病が課題としてありますが、最も恐るべき伝染病を駆逐したことは、特筆すべきことだと思います。(2007年5月)
おまけ
昨年末にお隣、韓国で強毒タイプの鳥インフルエンザが4例発生し、養鶏農場には原因と推測されている野鳥の侵入防止対策を鶏舎や飼料倉庫、飲水設備を含めて今一度確認してくださいと連絡していたところですが、1月11日宮崎県で鳥インフルエンザの疑いという一報が入ってきました。宮崎県では、直ちに防疫体制をとり、発生農場および周辺農場の対応を極めて迅速に終えています。3年前の山口県での発生以来、各県ともいろいろな防疫演習を行い、対策を練って来ましたが、その成果でしょうか。宮崎からの第一報以降、長崎県では、養鶏農場の立入検査を実施し、異常のないことを確認しましたが、併せて宮崎県が実施した防疫対策の実際を勉強し、今後に活かす必要があるでしょう。
迅速に処理された鳥インフルエンザですが、一方で、人の新型インフルエンザが危惧されており、そちらに関する質問も受けることがあります。人の健康問題となれば、獣医師では多少越権行為(?)ですが、わかる範囲でお答えしています。ただ、そういった質問の中で、「現在、鳥インフルエンザが流行っていますが・・・、」で始まることがあります。「流行っていません!」まずそう答えないといけないのが残念です。宮崎県の事例では、農場の3つの鶏舎のうちたった1つの鶏舎での発生であること、周辺の農場の検査ではいずれも陰性であること、発生情報を受けた各県の検査でも異常のない事など、新聞やテレビで多くの情報がもたらされたと思っているのですが、発信する側と受ける側の違いとでもいうのでしょうか。(2007年1月)
宮崎県の鳥インフルエンザ情報
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、近年、非常にクロースアップされているのが、ペットや家畜を含めた動物から感染する病気です。つい最近、海外から帰ってきた人が発症した狂犬病などが代表選手ですが、そのほか、食の安全問題で取り上げられるサルモネラ食中毒や今、世界的に危惧されている新型インフルエンザが発生すれば鳥インフルエンザもその1つになります。これまで、人の伝染病は天然痘や赤痢など多くが征圧され、もう心配が無いと思われた時期もあったようですが、戦いはまだ終わっていないということです。特に、これまではあまり知られていなかったのに、あるいは、もう過去のものと思われていたのに、近年被害が報告されるようになったタイプに、実は動物由来感染症が増えています。30数年ぶりに確認された狂犬病では、感染発症すれば致死率ほぼ100%と報道されていましたし、新型インフルエンザやBSEなど恐ろしい病気が多いのですが、だからといって、そのまま身のまわりに居るペット達が全て危険というわけでは無論ありません。やみくもに恐れるのではなく、正しい情報知識を知っていただきたいと思います。
これらについては、厚生労働省で情報発信されていますので、ぜひそちらで正しい情報を得ていただきたいと思います。(2006年11月)
ホームページ動物由来感染症を知っていますか?
つい最近、子どもが通っている小学校のクラス(3年生)でゲストティーチャーと持ち上げられて、獣医師の仕事の話などしに行ってしまいました。先生からお話があった時は、何でもいいからお父さんの提供できる話題を、ということだったような気がするのですが、やはり何らかの教育的な(?)テーマを入れ込んでということでまとめてみました。ところで、食育っていったい何?食の安全安心?これは難しいテーマでしょう。
さて、のどかな牧場の牛はいったい、なんのためにいるのか?さらに、みんなが大好きな焼肉やトンカツ、唐揚げの元は・・・何?これはあまりにストレートかと思い、初心者相手では、なるべく刺激的でない卵と牛乳の話を携えて行きました。卵も牛乳も本来
鶏を飼うということ
鳥インフルエンザがまた話題になるかもしれない季節が、近くなりました。一般の養鶏場のほかに、自分たちがあまり実態を知らない、ごく小規模の鶏飼養者の対策を強化すべく、最近の地産地消の取り組みのなかで増えてきている直売所をめぐり、そこに鶏卵を出荷している方々を対象に、調査をしました。おかげで、直売所担当者の協力を得て、ほとんどの方と色々お話しできて、資料もお渡しすることが出来ました。でも中には、「何でうちみたいなほとんど自給のみの鶏まで取り締まるのか、おかしな事はしていないのに」との反論も受けました。我々は、けっして取り締まってはおりません。ただ、伝染病は、飼養規模の大小を選ばずに降りかかりますし、そのための対策も規模の大小に関わらずするべきものであると思います。その方法や病気の情報などは、鶏を飼っている方にはできる限り平等に伝えるべきでしょう。何か事があってから、知らなかったではすまないと思うのです。以前、鳥インフルエンザ国内発生のあった時、「あそこに飼ってある鶏は大丈夫か」という相談電話等も多かったので、鶏飼養者の中にはプレッシャーを感じている人もいるのかしれません。我々の話や資料をもとに、「これこれの対策をしている」、「家畜保健衛生所の人もそうすればいいよと言った」と答える材料にしてくれればいいなと思いながら対応してます。(2006年11月)
ポジティブリスト制度って
畜産農家に行って説明をしていると、言う方も聞く方もしまいには舌がまわらなくなる言葉です。
もともと食品には、例えば農薬や抗生物質などに厳しい残留基準が設けられ、残留があれば食品として認められない、そのためには出荷何日前になると使えないという期間が決められていました。そして、検査機器の進歩で検出精度がどんどん上がり、厳しくなる一方でした。さらに、外国からの輸入農産物が増えてくると、国内基準が決められていない薬品類も対象にする必要が当然出てきます。そこで、これまで基準が決められていた薬品類のリストを増やした上、リスト以外の類についても一律に0.01ppmという基準が決められました(これがポジティブリスト制度)。
厳しいようですが、実はごく普通にやっていればクリアが可能な基準である事も事実です。消費者サイドとしては、じゃあ期限ぎりぎりまでは使っていいという事か、という疑問があるかも。しかし、生産者としては、なるだけコストを減らしたいところで、どこを削るかを日々研鑽しているような状態です。出荷前何日からは使わないというより、家畜でいえば何日齢を過ぎると一切薬品類を使わないというのが現状です。最も、管理はやりっぱなしで、病気の恐れもたぶんにあり、予防として薬が手放せないというのであれば、コスト削減など無理な話。日頃から衛生管理を徹底し、最小限の薬剤を有効に使って、安全安心な生産に努める。そして今後はそれらを記録していくことが証となります。(2006年9月)
BSEその後とアメリカのBSE問題
長崎県で、そして黒毛和種で初めて発生したBSEは、その後波紋の広がりもなく、お陰様で風評被害もなく、平穏な日々を取り戻しつつあります。今後も、できる限り正確な情報の提供をすることが最低限の条件でしょう。で、現在話題となっています(?)アメリカからの牛肉輸入再開問題です。こちらもそれほど大きな話題になりきれないような気がするのは、「正確」な情報がもたらされて、冷静な判断ができるようになったと考えていいのでしょうか。アメリカにおいても今後は適切に対応がなされてくるし、なによりBSE、それから来る変異型のCJDは、実はよ~く考えてみれば、元々もの凄く小さな確率に一喜一憂したんだと言うことが明らかになったと言うことでしょうか。リスクゼロ要求は当然かもしれませんが、現実に可能なレベルが自ずと現れると思いますし、一方で、そのための努力は当然すぎるほど必要だと思います。そういうことも含め、今、国内の生産者は飼料や薬剤などの生産履歴を記録する取り組みが始まりました。(2006年8月)
長崎県初のBSEについて
平成17年度末に起こった長崎県のBSE騒ぎは、畜産関係者にとって、まさに青天の霹靂。国内24例目となった牛は、長崎県壱岐島の生まれで、14歳になる黒毛和種の繁殖母牛でした。BSEは、これまでの研究の成果から、生後1年以内に食べたエサに原因があると考えられ、数年を経て発症するもので、他の一般的な伝染病のように発症牛から横に広がっていくことはないことなどが解っています。今回の対応として、発症牛は焼却処分され、当然市場には出回りませんし、関連牛の調査から、発症牛と同時期に生まれた2頭、それから、発症牛が生んだ子牛1頭が感染を否定できない牛と判断され、同歳の牛は焼却処分されました。但し、検査結果では、BSE陰性と判定されています。また、子牛は今後のために研究機関で調べられることになりました。
死亡牛も含めた全頭検査やこれまでの研究成果、情報の積み上げのおかげでしょうか、当初は騒然としましたが、新聞等も比較的冷静な扱いであったと思います。もちろん、今後のために疫学調査が重要なのはいうまでもありません。(2006年4月)
豚インフルエンザについて~「史上最悪の病原菌」豚インフルエンザ発生、死者100万人?大統領恐怖の会見
サブタイトルは、最近放映されたテレビ番組の新聞予告欄に記載されていたものです。昨今、鳥インフルエンザや新型インフルエンザの脅威がマスコミを中心に騒がれていますが、豚インフルエンザとは?豚も危ないという話になっていくのでしょうか?インフルエンザウイルスは元々、鳥のウイルスと考えられていますが、現状で人や馬、それからアザラシやイルカの様な海獣にも感染することが知られています。豚のインフルエンザもそんな一つですが、タイプでいうとH1N1及びH3N2。これが養豚農場で、散発的に発生しています。鳥インフルエンザとの違いは、まず日本でも豚に発生があること、次いで、人のインフルエンザと同様に伝播力は強烈ですが、適時に対応して、肺炎を誘発させなければ何とかやり過ごせること、さらに、何といってもHやNのいわゆる亜型が人に流行しているインフルエンザと同じだということです。毎年流行する人のインフルエンザは、亜型は同じでも微妙に違いがあるようで、用意されたワクチンの効果がなかなかすっきりと現れない年もあります。そう考えると、同じタイプとはいえ、豚インフルエンザも人に流行すればそれなりの疾病になると推測されます。しかしながら、人と豚という種のハードルはやはり高いようで、そうはなっていないのが現状です。
新型ウイルスが豚から生まれてくるという説も唱えられていますが、これにしても、まず鳥インフルエンザありきです。鶏に鳥インフルエンザの流行があって、同じく人に人インフルエンザが流行していて、何らかの機会で、1頭の豚の体内で混ざった場合に新型ができる可能性があるわけです。当然、何もない豚からにわかに新型ウイルスが湧き出るわけではありません。日本においては、少なくとも現時点では、新型インフルエンザを闇雲におそれる必要はないと思われます。もちろん、それぞれの担当部門の事前対応は必要ですが。
冒頭のテレビ番組では、豚インフルエンザがかって全世界で2000万人の死者を出したと放送されましたが、それは20世紀初頭に大流行したスペイン風邪ことを言いたいのでしょう。原因ウイルスは、亜型でいえばH1N1で、豚のインフルエンザと同じですが、やはり鳥型がなんらかの手段で人に流行する様になったと考えられています。あえて、豚インフルエンザとする根拠は薄いようです。しかも、事件として報じられた伝染病は、実際はレジオネラ菌による全く別の病気のことでしたので、ちょっと拍子抜けする番組でした。でも、この時期にあえて豚の風評をあおりかねない番組の作り方というのはどうなんでしょう。(2006年1月)
鶏は大丈夫でしょうか?
新型インフルエンザの危機がマスコミで報道されるようになると、早くも「うちで飼っている鶏は大丈夫でしょうか?」、「学校の鶏や小鳥は大丈夫でしょうか?」という問い合わせがありました。この大丈夫は、鶏の健康ではありません。人に害を及ぼす可能性を心配されているのです。ところで、本来、家畜保健衛生所は、獣医師として、畜産業に被害をもたらす伝染病の防疫対策を仕事にしており、人の健康相談は、いわば越権行為(?)であるかとも思いますが、大きな意味では、動物由来感染症に関係する対応の一環ということで、知る限りの情報をお伝えしています。
新型インフルエンザの前提として、まず鳥インフルエンザの流行があります。その中で、人への感染力を持ったウイルスが発生した場合が、いわゆる新型インフルエンザにつながります。この1点に誤解がないようにしていただきたいのです。外国で、鳥インフルエンザに感染して人が亡くなったという報道と目の前で餌をついばむ鶏とは、この時点では、関係がないということです。インフルエンザといえども沸いて出るわけではありません。やはり何らかの接点がないと感染は起こらないのです。まして、目の前の鶏にどのような危険性があるのでしょう。そんな状況下で、あたら騒ぎを大きくしていいのでしょうか。 そうはいっても、危険をもたらす可能性がわずかでもあるものは、あらかじめ排除しておく気持ちは分からなくもないですが、その一方、生き物を飼う人の義務もあるのではないでしょうか。ペットの生き死にをその手に握っていることの重大さを考えてほしいと思うのは、この場合、的外れなのでしょうか。(2006年1月)
学校飼育動物に限らず、愛玩全般に対し、知識や情報が豊富なHPを紹介します。
学校飼育動物を考えるページ
TVや週刊誌で鳥インフルエンザ情報が増えてきました。しかし、趣旨は鳥インフルエンザではなくて、「新型インフルエンザが発生したなら」、という扱いです。鳥インフルエンザウイルスが鳥から人に感染し、さらに人から人へ感染する能力を得た場合を新型インフルエンザ。東南アジアでは100人以上が感染し半数以上が死に至ると伝えられています。人になじみがない、つまり免疫がない、悪化が予想される、ということで、TV等で伝えられるように、20世紀に何回かあった世界的な流行が再現されてしまうのでしょうか。
状況を整理してみます。現在、鳥のインフルエンザの発生報告が世界各地からあっています。また、東南アジアなどで人への感染が報告されています。インフルエンザウイルスは変異しやすいということであり、人から人へ感染流行する新型が生まれる可能性は高まっていると言えるかもしれません。しかしながら、現状では人から人へ感染するということは、未だ認められていないというのも厳然たる事実です。仮に新型の発生報告があったとしますと、対策は感染した人からの感染防止になります。うがい、手洗いの励行や人混みを避けるといった、いわゆるインフルエンザ対策を厳密に実行する事がまず必要になるでしょう。状況により抗ウイルス剤も服用することになるのでしょうか。
ところで、日本でも、鳥インフルエンザが地域的に問題となっており、防疫対応が続けられています。汚染物などは焼却され、ウイルスの飛散防止が徹底されています。季節的に渡り鳥の飛来を考えると、国内の鶏たちに、感染の可能性を完全に否定することはできませんが、けっして流行しているわけではありませんし、もちろん店頭に並ぶ鶏肉、鶏卵は全く安全です。現状を考えると、国外での新型発生に気を配る必要があると思います。その際には、もう鳥は関係なく、人の病気として対応が重要になります。
今後はまず、鶏での発生情報について、的確な把握と対応が必要でしょう。その点は、畜産現場の業務上当然の義務であり、日頃から気がけているところです。そういうことで「流行っている」、「鶏を飼っているが不安だ」、「どこそこの鶏は大丈夫か」といった相談には、できる限り答えていきたいと考えています。(2005年12月)
新聞情報では、アメリカ産牛肉の輸入が再開されるようです。一昨年のアメリカでのBSE確認依頼、日本のみならず輸入国側では、安全性の確認を強く要求していた訳ですが、日本ではここに来て食品安全委員会が、日米のリスクの差は小さいと判定し、政府判断に委ねたということです。元来、BSEの発生予測はかなりゼロに近いとされますし、その中でも敢えて強固にゼロリスクを要求し続けてきたと思うのですが。アメリカの言い分は、早急に受入体制をきちんとして、ということでしたが、これはいったいどうなんでしょう。生産側であるアメリカの対策こそどの程度整ったのでしょうか。日米双方で、科学的判断というより、政治的判断も感じるのですが。
ところで、輸入してはたして売れゆきはどうなるのでしょう?TVを見ていると、「食べるかどうかは自己責任で決める」という言葉が気になりますが、命の基礎になる食の安全性は、はたして自己責任でいいのでしょうか。(2005年11月)
アメリカのブッシュ大統領が新型インフルエンザ対策に70億ドル、実に8000億円もの対策を発表したようです。いつのまにか世界各地から鳥インフルエンザの情報が入ってきています。
鳥インフルエンザは他の多くの家畜疾病とは一つ大きな違いがありますが、それは、「もしかして人に感染するのではないか。」、これが、騒ぎを大きくする理由でしょう。高病原性鳥インフルエンザといいますが、これはあくまで鳥に高病原性であるということ。また、発生があれば、鶏等の移動制限がかけられますが、これは周辺の養鶏産業に拡大するのを阻止するためで、人への影響を防ぐ意味ではありません(もちろん、人に感染しないということです)。しかしながら、現実に東南アジアなどで人の感染死亡例があります。国によっては、人の生活圏内に鶏が密接に関わっている地域があり、そのような条件下での偶発的な感染といわれていますが、ひょっとしてその中で人から人へ感染する能力を得た新型ウイルスが出現するかもしれない。その脅威が話題になっています。
もし、そうなれば20世紀初頭に世界で流行したスペイン風邪を越える伝染病となるだろうと予想されており、アメリカのみならずEU、もちろん日本でも対策会議が立ち上げられています。あくまで万一の危機対策で、始まったばかりですが、状況に応じた正確な情報の提供というのは最低必要条件であることは確かです。我々としては、その前の段階、つまり鳥に高病原性鳥インフルエンザが発生するのを防ぐ努力(結果として、新型を発生させない)を精一杯するというのがまずなにより必要なことだと思います。(2005年11月)
茨城県で発生した鳥インフルエンザについて考えてみたいと思います。臨床的には産卵率の低下があっただけで、平成16年冬に山口県や京都府で見られた高い致死率はなかった、季節的にも日本では沈静に向かうと思われる夏季に近い時期であることなど、疑問点はいろいろあります。茨城県での発生というのも想定の範囲外と言えるかもしれませんし。ウイルスはH5N2亜型。昨年末、韓国での単発例と同型ですから、どういう伝播ルートが考えられるのだろうと思っていましたら、農水省の検査では、南米のグアテマラで検出されたウイルスに近似していると発表され、ますますわからなくなりました。
これまで、養鶏農家に立入検査や研修会などでお知らせしていたことにも修正が必要になってくるかもしれません。いきなり爆発するのではなくて、実は静かに侵入してくることもあるのだと。わからないことだらけですが、だからこそ調査の必要性があると思います。ウイルスが静かに広く浸潤しているのでは?という心配も心をよぎりますが、なにしろ、最も恐るべきは、知らない間に広がって、ある日突然爆発することなのではないでしょうか。ここに、弱毒タイプでありながら高病原性鳥インフルエンザに位置付けられている理由があります。
特に異常も見られない状況下でも、やはり検査により清浄性を確認する作業は重要であると思いますし、養鶏農家への説明と理解を求めることを併せて進めることになります。(2005年7月)
すっかり暖かくなり、鳥インフルエンザの脅威もずいぶん遠のいたようですが、東南アジアでは依然発生中で、しかも人の感染情報も聞こえてきます。日本では昨年来、各県が防疫のためのマニュアルを作成し、対策を整備しました。研究機関では、人の新型インフルエンザワクチン開発に着手し、ほぼめどが立った様子。昨年あれほど騒がれたのに、今冬が平穏だったのはこれらの対応が認められたから?
一方、BSE。アメリカからの牛肉輸入再開はどうなんでしょう。アメリカが主張では、日本の厳しすぎる基準は世界的でないし科学的でないとのこと。これについて日本の世論はどうなんでしょう。もし、厳しすぎる基準はいらないのではないか、そして、アメリカ牛肉輸入再開という声が大きいというなら、全頭検査が始まった当初のオーバーヒート加減が、冷静に再考して科学的対応をする状況になったと考えていいのでしょうか。とはいえ、我々にできることは正確な情報を伝え、疑問には的確に答え、対応は迅速に、ということでしょうしそれが義務でもありましょう。(2005年5月)
消費者向けの話などでは、豚には肺炎が多いとされており、確かに生産現場では豚といえば肺炎対策といっても過言ではないようです。ところで、いろいろ考えますと畜産では肺炎という言葉を軽く使っていないかという気がしてきます。肺炎という言葉には、もっと重いイメージがあるのではと思うのです。ずっと昔の小説では、「肺炎」は不治の病の役割を担っていたのでは?。とすれば、豚には肺炎がある、と言うと、生産側で思っているより消費者側では非常に病的なイメージを思い浮かべているのではないでしょうか。現場としては、肺にわずかでも病変があれば、何々性肺炎という診断名が、獣医学用語としてつけられます。農場で見つかる場合は、熱が出たり、えさを食べなかったりして、やせたり時に死ぬものもあり、出荷されていく豚としての群から外れていきます。生産者としては、そのような診断は、対策を検討することになる貴重なデータ還元ですが、一方、消費者側からすれば、「肺炎と診断された豚」から受けるイメージは多大なものがあるのではないでしょうか。肺炎という言葉に生産側と消費側で軽重があるということは重要であると思います。(2005年3月)
病気だらけの肉?!
食肉として処理される豚の70%がなんらかの病気を持っている?本だか何かで知人が仕入れてきた情報です。あたかも店頭に並んでいる肉は病変部位をそぎ落として整形した肉であるかのような印象を受けていたようですがその真偽は?
豚でも牛でも、食肉センターに出荷するとまず獣医師による診断があります。万一、何らかの異常があれば持ち帰りまたは処分です。センターは当然ながら多くの農場からトラックが集まるわけですから、簡単に病気を持ち込まれては大きな影響を及ぼすからです。もちろん農場側としてもお互いのことですから、疑いのかかりそうな家畜を安易に出荷できません。さて無事、獣医師の診断をクリアした家畜は、食肉として処理されますが、肉や内臓など各処理段階でやはり獣医師の目が光っています。ちょっとした傷や出血、外見的には見つけにくいわずかな病変部もチェックが入ります。冒頭の数字からいけば、これらの関門をすべてパスできるのが30%程度となるのでしょうか。実際のところは、はねられる原因のほとんどは肺に集中しており、変色、小出血、軽度の炎症跡などです。可食部分、つまり肉や内臓に異常があるなんていうのはまず見かけません。こういうものは廃棄され、食肉に出回ることはありません。(2005年2月)
一般誌やテレビで報道されるくらいに玉子の小売価格が目立って上がっています。玉子1パック200円超なんて言うのは、ここ数年では珍しい事でしょう。鶏卵は数年来、安値が続き、今年の始めには流通レベルで1kg100円を割り込んでいました。その上に鳥インフルエンザの影響で直接あるいは風評被害もあり、壊滅的な打撃を受けたのですが、やっと最近になって回復、さらに当時の影響で生産量が減り品薄となったのが原因でしょう。
とはいえ、農家といえば豊作では値段暴落、値段が上がるのは凶作で品薄の時。値段がいいからといってホクホクとはいかないようです。でも鳥インフルエンザや台風など、いい話が無い中、少しは生産者の元気材料になって欲しいもの。消費者の皆さんもご理解よろしくお願いします。 (2004年11月)





